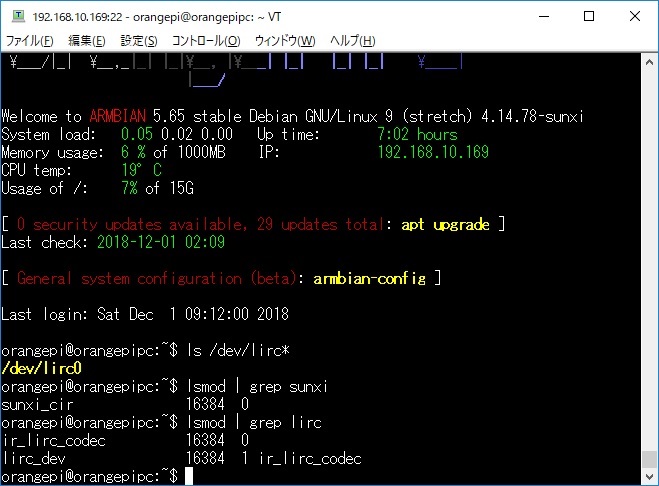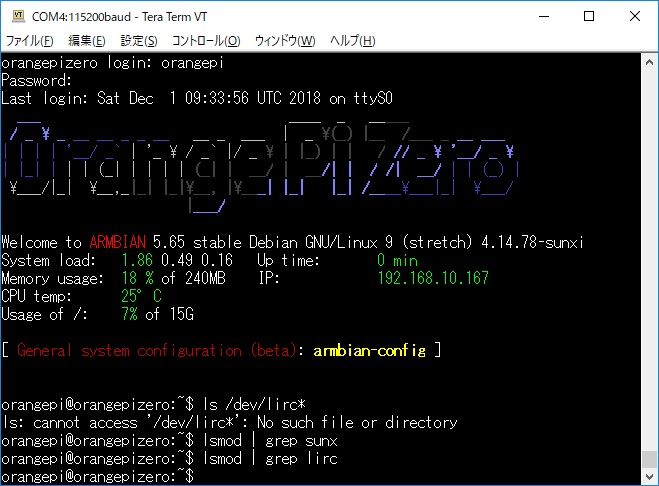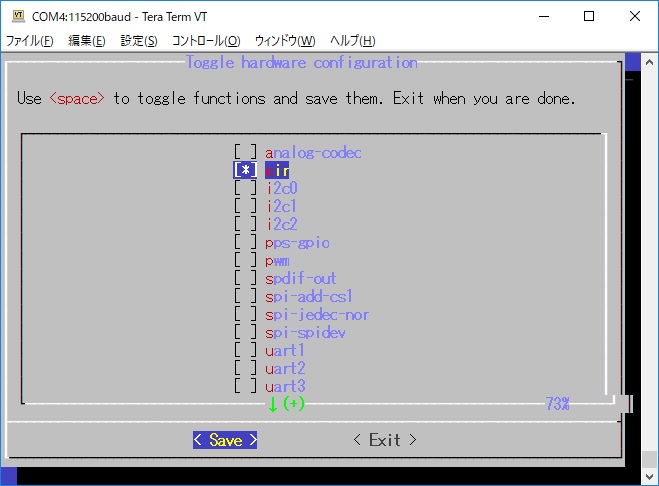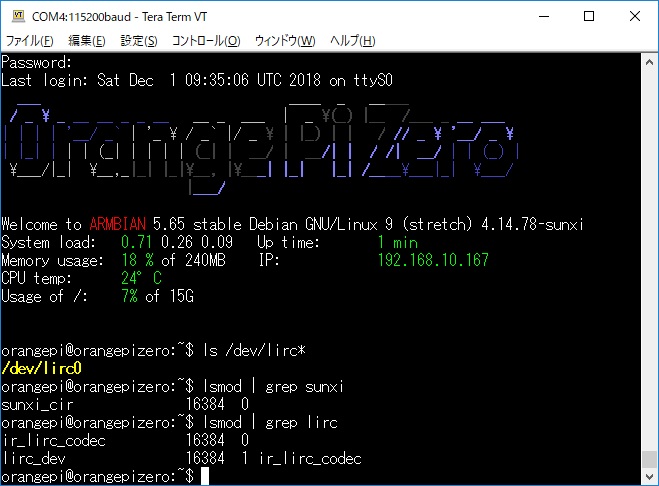orangepi@orangepizero:~$ irw
0000000000ffa857 00 ok kodac
0000000000ffa857 01 ok kodac
0000000000ffc23d 00 menu kodac
0000000000ffc23d 00 menu kodac
0000000000ff906f 00 right kodac
0000000000ff906f 01 right kodac
0000000000ff9867 00 down kodac
0000000000ff9867 01 down kodac
|