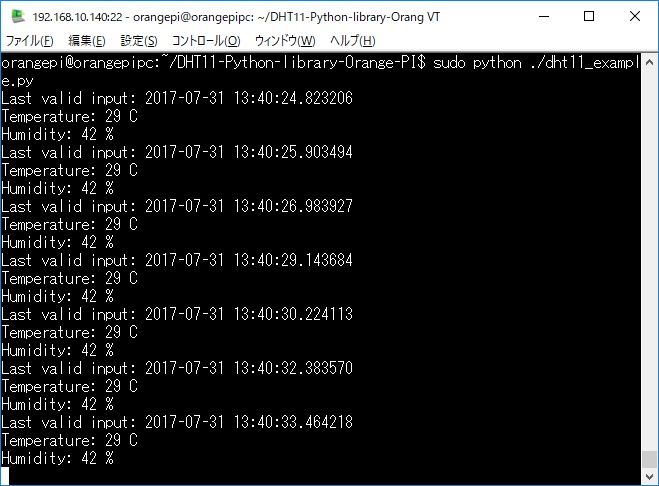len(data)= 647
ディジタル入力で647個のデータを入力しています。
データの中身はディジタル値(1 or 0)で、647個の0/1がずらずらと並んでいます。
同じ値(正確には1が)100回連続するとデータの終了と判断しています。
len(pull_up_lengths)= 40
[4, 3, 10, 3, 10, 11, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3,
4, 11, 10, 11, 10, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 11, 4, 4,
11, 4, 10, 4]
LOW(=0)が1回でも出現するまで、何回HIGHが連続するかを数えます。
上の例では以下のようなデータになっています。
HHHH
HHH
HHHHHHHHHH
HHH
HHHHHHHHHH HHHHHHHHHHH
L....L
L...L
L....L
L...L
L...L
L...L
ここでのLOWはデータの区切りを示しているだけで、連続する個数は意味が有りません。
次に、Hが続く個数の最大個数と最小個数を求め、その平均値を求めます。
最大個数→11
最小個数→3
平均を求める
3 + (11 - 3) / 2 =
3 + 8 / 2 =
3 + 4 = 7
[False, False, True, False, True, True, False, False,
False, False, False, False, False, False, False, False,
False, False, False, True, True, True, True, False, False,
False, False, False, False, False, False, False, False,
True, False, False, True, False, True, False]
上記の7を閾値としてHIGHの連続個数をTrue/Falseに変換します。
連続個数が7を超えるとき→True
それ以外→False
[4, 3, 10, 3, 10, 11, 3, 4.... → F, F, T, F, T, T, F,
F.....
True/Falseを8個ごとに分解します。
①False, False, True, False, True, True, False, False,
②False, False, False, False, False, False, False, False,
③False, False, False, True, True, True, True, False,
④False, False, False, False, False, False, False, False,
⑤False, True, False, False, True, False, True, False
これをTrue→1 False→0として16進に変換します。
①00101100 = 0x2c
②00000000 = 0x00
③00011110 = 0x1e
④00000000 = 0x00
⑤01001010 = 0x4a
①から④のCheckSumを計算します。
(0x2c + 0x00 + 0x1e + 0x00) & 0xFF = 0x4a
⑤と一致するのでデータは正常です。
0x2c 0x0 0x1e 0x0 0x4a
DHT11は8ビットの分解能なので②④は常に0です。
0x2c = 44 → 湿度
0x1e = 30 → 温度
Last valid input: 2017-07-31 13:00:44.233506
Temperature: 30 C
Humidity: 44 %
|