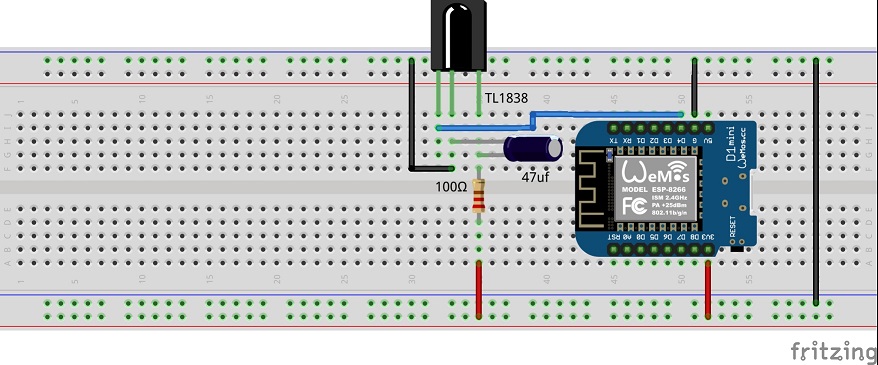
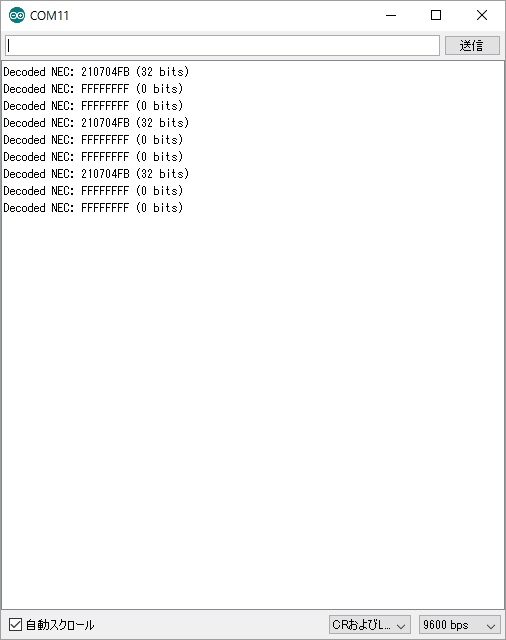
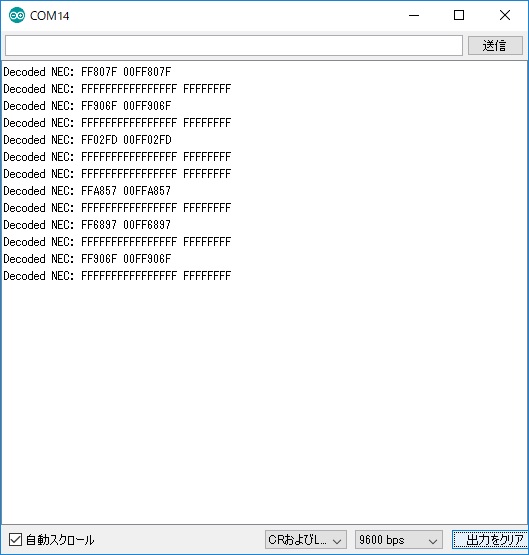
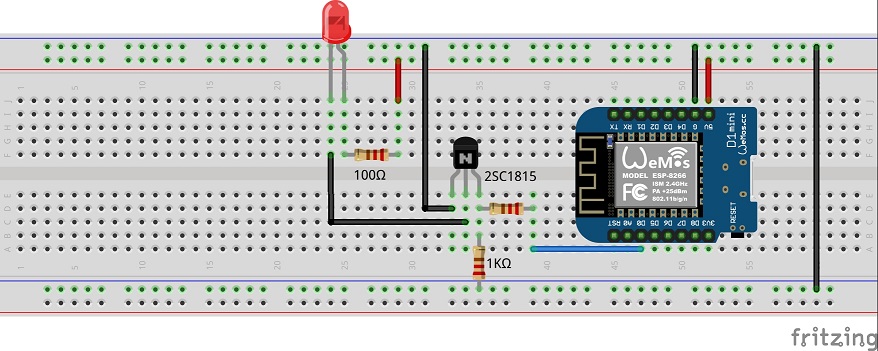
/* |
| Model | Product | AGC Type |
Transmission distance |
Minimum irradiance |
Directivity (Viewing Angle) |
Supply Voltage |
Supply Current |
PinOut | Width/Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOP17 | TSOP1738 | 35M | 0.35mW | ±45Deg | 4.5〜5.5 | 0.6mA | GND/VS/OUT | 10/12.5 | |
| TSOP18 | TSOP1838 | 35M | 0.30mW | ±45Deg | 4.5〜5.5 | 1.2mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP2 | TSOP2138 | AGC1 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.7mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 |
| TSOP2238 | AGC2 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.7mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 | |
| TSOP2438 | AGC4 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.7mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 | |
| TSOP4 | TSOP4138 | AGC1 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.7mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 |
| TSOP4838 | AGC2 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.7mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP4438 | AGC4 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.7mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP31 | TSOP31138 | AGC1 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | GND/VS/OUT | 10/12.5 |
| TSOP31238 | AGC2 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | GND/VS/OUT | 10/12.5 | |
| TSOP31338 | AGC3 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | GND/VS/OUT | 10/12.5 | |
| TSOP31438 | AGC4 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | GND/VS/OUT | 10/12.5 | |
| TSOP31538 | AGC5 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | GND/VS/OUT | 10/12.5 | |
| TSOP32 | TSOP32138 | AGC1 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 |
| TSOP32838 | AGC2 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 | |
| TSOP32338 | AGC3 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 | |
| TSOP32438 | AGC4 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 | |
| TSOP32538 | AGC5 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/VS/GND | 6/6.95 | |
| TSOP34 | TSOP34138 | AGC1 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 |
| TSOP34838 | AGC2 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP34338 | AGC3 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP34438 | AGC4 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP34538 | AGC5 | 30M | 0.08mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 6/6.95 | |
| TSOP38 | TSOP38138 | AGC1 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 5/6.95 |
| TSOP38238 | AGC2 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 5/6.95 | |
| TSOP38338 | AGC3 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 5/6.95 | |
| TSOP38438 | AGC4 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 5/6.95 | |
| TSOP38538 | AGC5 | 24M | 0.12mW | ±45Deg | 2.5〜5.5 | 0.35mA | OUT/GND/VS | 5/6.95 |